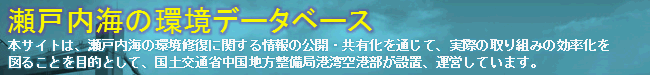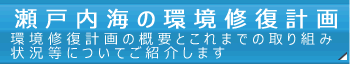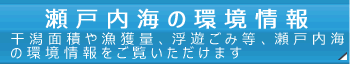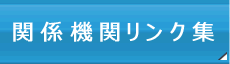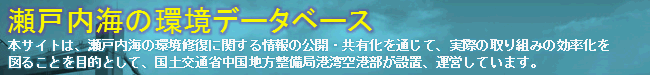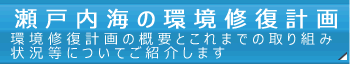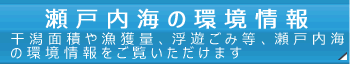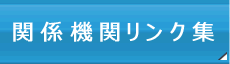|
|
|
|
|
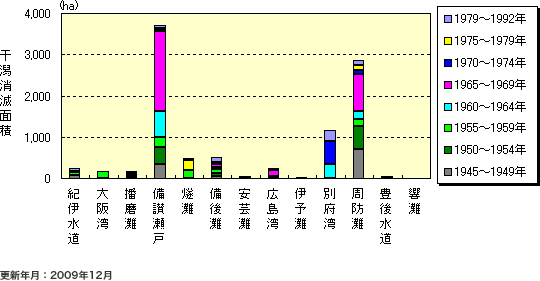
出典:自然環境保全基礎調査(第2回・第4回、環境省)

| 備讃瀬戸では、1969年までに4,000ha近くの干潟が消滅しており、特に1965-69年の間に約2,000haの干潟が消滅しています。また、周防灘においても1969年までに2,000ha近くの干潟が消滅しています。 |
|
|
|
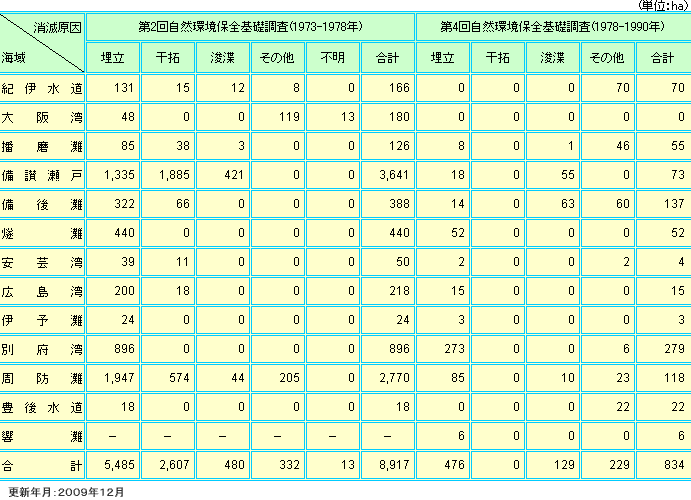
出典:自然環境保全基礎調査(第2回・第4回、環境省)
注)1.消滅原因が複数示されている場合は、複数の消滅原因に各々同面積が加算されている。
2.響灘では「第2回自然環境保全基礎調査」において、調査は実施されていない。

干潟の消滅原因には、埋立、干拓、浚渫といったものがあります。瀬戸内海全体では、いずれの年代においても埋立が主原因となっています。1945-1978年には、埋立が消滅原因の約60%を占めており、次いで干拓が約30%を占めています。1978-1990年には埋立が消滅原因の約60%を占めており、次いで、干拓でも浚渫でもないその他の原因による消滅が約30%を占めています。
海域別には、1945-1978年には、全ての海域で埋立または干拓による消滅が主原因となっています。1978-1990年には、備讃瀬戸、備後灘において主原因が浚渫によるものであったこと以外は、埋立による消滅が主原因となっています。 |
|
|